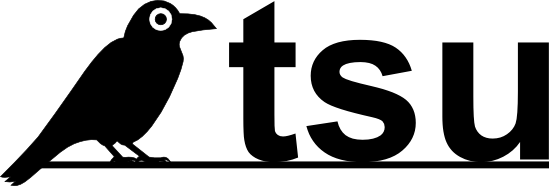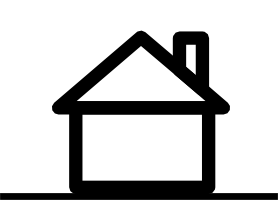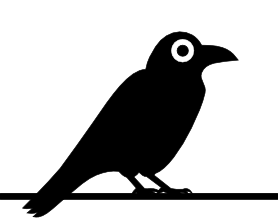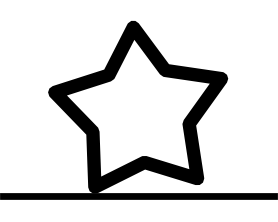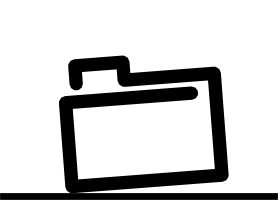この文章は、NPO法人「FENICS」の2020年12月25日発行のメールマガジンに寄稿したものです。編集・発行者の許可を得て、こちらに転載しました。
まとめ
ペルーでの調査に1歳4ヶ月の子供を連れていって得られた知見をまとめてみたい。
どんなに些細なことでも、サポートをもらえると本当にうれしかった。今回の調査では、3人の研究者のチームに私たちが合流したため、ひとりの子供に対して5人の大人がいた。食事の時間に早く食べ終わって子供を抱っこしてくれたり、離乳食のパウチを持ってきてくれていたり、ふだんから気にかけて一緒に遊んでくれたり。子供がいることで迷惑をかけていないかとびくびくしていたけれど、そのように接してもらえることで、手段的にはもちろんのこと、親たちの情緒的にも、本当にありがたいサポートをいただけていた。
一緒に行動する他人の目があることで、夫婦間の空気も穏やかなものになった (ように思う)。旅先では、慣れない環境での無意識のストレスと育児疲れから、夫婦のあいだのやりとりがトゲトゲしたものになりがちである。けれど、そこに他の人の存在があることで、憤懣を客観的に眺めることができて、悪い空気がエスカレートしていくのを防げていたように思う。
そして、余裕のあるスケジュールと十分な準備がきわめて重要だとわかった。特に小さな子供は、大人の都合にあわせてくれるだけの身体能力や聞き分けの良さを持っていない。したがって、大人が子供の都合にあわせる必要が生じる。子供の生活リズムを考慮したスケジュールで移動や調査の予定を組み、なにごとも詰め込みすぎないようにしたほうが良い。疲れた子供の相手で親も疲れて、お互いに風邪をひいたりして共倒れしてしまうと、回復にかなりの時間が必要になる。また、そうした危機を未然に防ぐため、現地調達の可能性をあてにせず、持っていける育児関連のモノはできるだけ持っていったほうが良いかもしれない。
しかし、子供の性格、年齢、発達段階や、調査地や調査の性格によっても、ベストなやり方は変わってくのではないかと思う。私たちの場合、子供は当時体重8−9 kgだったため、航空機の乳児用バシネットを使えたが、もっとふくよかに育っていたら、飛行機移動のあいだずっと膝に抱えていなければならなかったかもしれない。また、はいはいではなく歩くこともできたため、床のほこりなどはあまり気にせずに済んだ。その一方で、まだおっぱいを吸っていたため、(主に妻のほうで) 授乳場所の確保や夜間授乳が大変であった。また、まだおむつが取れていなかったので、大量の紙おむつにスーツケースの空間が占拠されることとなった。子供が1歳4ヶ月だった当時は離乳食パウチをたくさん持っていくのが正解だったけれど (自分たちで持っていった分だけでは足りず、なんと共同研究者が持ってきてくださった分をありがたく頂戴した)、2歳になった今は別の偏食がはじまっており、もし今連れていくとしたら、食事に関してはまた違った戦略を考えなければいけないように思う。
大変なことの多い子連れフィールドワークではあるけれど、得がたい経験であることも確かだ。子供の生活リズムにあわせることで、そうでなければ気づかない調査地の一面が見られたり、手を動かせない時間が増えるので思いがけない着想が浮かんだりもする。子供を介して現地の人たちとコミュニケーションがとりやすくなるのも利点かもしれない。子供のほうも、普段とは違う環境でなにかを学んでいるようだった。たとえば、日本の通常の暮らしではまず見ることのないウシやヤギが飼われているのを間近に見て、調査期間中に「もーも」と「めーめ」という言葉と概念を会得した。調査や研究に関する効率はどうしても半分以下になってしまうから、積極的にお勧めできるものでもないけれど、どうしても子連れでフィールドに行かねばならないなら、やってみれば意外となんとかなりますよ、と私は思う。
最後に、調査を率いてくださり多大なる配慮とサポートをくださったWさん・Nさん・Kさん、そして対等なパートナーとして妻に、この場を借りて改めてお礼申し上げます。